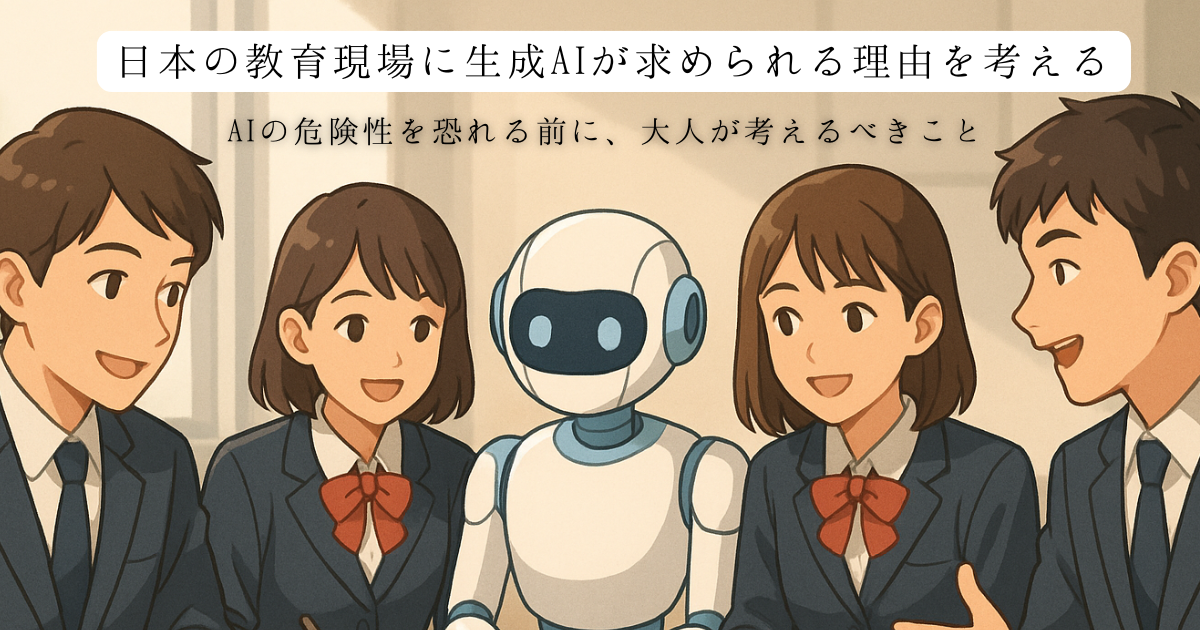最近、子どもたちの生成AIの利用について色々な方から「生成AIってどうなの?」「教育で使っていいの?」という相談や疑問をいただきます。今日は、これから数年後に社会で活躍する高校生や大学生向けに生成AIの活用について考えてみたいと思います。なお、中学生や小学生などは、またちょっと違う論点が必要だと思うので、改めてまとめる機会を持てればと思います。
日本は生成AIの「利活用しやすい国」なのか?
日本政府は近年、生成AIを明確に国家戦略の一つとして位置づけています。その背景にあるのが、日本の抱える最大の課題のひとつ「少子高齢化」です。内閣府の統合イノベーション戦略推進会議で2023年6月8日公表した資料「AIに関する暫定的な論点整理」では、以下のような記述があります。
「そもそも労働人口が急減する日本においては、生産性を上げていくことは避けて通れない道であり、社会全体でAIを利用することの必要性は論を待たない。」(p.5)
引用:AIに関する暫定的な論点整理(2023年6月8日)
さらに、産業革命期に日本が内燃機関を吸収し、自動車産業を興した過去を振り返りつつ、次のように述べられています。
「産業革命時には内燃機関という新しい技術をすみやかに吸収し、独自の改良を加え自動車産業を興して世界のトップランナーとなった。…今回のAI変革期はどうか。」(p.5)
引用:AIに関する暫定的な論点整理(2023年6月8日)
これは、生成AIのような新技術こそ、日本が再び世界で存在感を示せるチャンスだという問題提起です。事実、ヨーロッパやアメリカと比較してもすでに現状の法制度における解釈や法的見解もかなり議論が進み、リスクはあると理解はしつつもまずはやってみるという精神のもと、行政への早期利用、特にデジタル庁が自ら導入し、省庁や自治体にも早期に横展開していく流れが見えている。欧米に比べ、初期投資と法的リスクが低く、PoCから社会実装までの距離が短い。もっとも、生成AIが出力した権利処理やサイバーセキュリティや利用者の倫理観や手軽さゆえの問題、高精度なインフラやそのインフラを稼働させる電力問題など課題は色々あるが、AI新法が施行され政府直轄の推進組織がこれら“次の宿題”にも解決していく準備が整っている。
2025/7/14のReHacのyoutube動画で語られた「日本は世界一!?AI戦略どうすべき?」で平将明デジタル大臣と松尾 豊東京大学大学院工学系研究科 教授 AI戦略会議 座長が語る対談からも詳しく読み解くことが出来るので参考までにリンクを貼っておきます。
制度面でも日本は前向き(最新の動向も踏まえて)
文化庁は、生成AIと著作権に関する最新の整理を発表しています。(文化庁『AIと著作権について)
あえて誤解を恐れず、分かりやすくポジティブにまとめると以下のポイントになります
- AIに学習させる目的なら、著作物のデータ利用は原則自由
→ AIの学習・解析目的なら著作権者の許可は基本的に不要(著作権法第30条の4) - 生成AIをビジネスで活用することに特別な制限はない
→ AIを用いてコンテンツ制作や業務活用すること自体は現行法上OK。ただし、生成物が他者の著作物を侵害していないかのチェックは必要 - 生成AIで作ったコンテンツも、人の工夫や創作があれば著作物になり得る
→ 完全自動生成だと著作権は認められないが、人間の創意工夫(指示や編集など)が加われば著作権保護対象になる可能性あり
このように制度環境が明確に整理されていることから、日本は世界的に見ても「生成AIを積極的に使いやすい国」になりつつあると考えることができます。新しいルールを恐れるのではなく、むしろルールが整った今だからこそ、教育現場をはじめとする社会全体で生成AIの活用について積極的に考えていくことが重要になっているのです。
文化庁の著作権セミナーはYoutubeでも公開されているので関心がある方はぜひ一度見て頂けるとよいかと思います。
教育現場が生成AIの導入を「急ぐ」理由――探究学習から進路選択、そして将来の職業選びまで
文部科学省は生成AIの利用に関してWeb上でガイドラインを発表しています。その中でも2024年12月26日、『初等中等教育段階における生成AIの利用に関する暫定的なガイドライン(Ver2.0)』を発表しました。「生成AIを使うのは何となく不安」「そもそも生成AIってそんなに便利なのか?」という漠然とした不安感がありましたが、このガイドラインによって「一定のルールのもとで前向きな活用が可能である」という方向性が明確になったと思います。
その上で、教育現場で生成AIを導入する動きが急に進んだように見えるのでしょうか?
実はこれ、決して突然の変化ではありません。もっと言うと、生成AIという「よいテクノロジー」が誕生したことによって、教育の在り方が抜本的に変わるかも?と捉えてみることが大切だと考えています。背景を紐解けば、20年以上積み重ねられてきた教育改革の延長線上に「生成AI」を位置付けることができるのではないでしょうか。
1998年に文部科学省が導入を決めた「総合的な学習の時間」は、2002年から全国で本格的にスタートしました。「生きる力」をテーマに、予測困難な社会に対応する能力を育むことが目的です。まさに今の現代社会に求められるものです。
その後、2018年には「総合的な探究の時間」へと進化し、「自ら問いを立て、情報を集め、考え、表現する力」が重視されるようになりました。さらに2019年にはGIGAスクール構想が始動し、コロナ禍によるリモートでの学びが必要になったこともあり、一気に児童生徒1人1台の端末と高速通信ネットワークという、生成AIを使える環境が全国の学校で整いました。
つまり、「探究型の学び」と「ICTインフラの整備」が重なりあったところに「生成AI」が登場したことで、教育に本格的に取り入れることが可能になったというわけです。
特に「総合的な探究の時間」は、生成AIと非常に相性が良い領域です。
- 問いを立てる力
- 多様な情報から自分なりに考える力
- 他者と協働して考えをまとめる力
これらが探究学習の中心的な目的ですが、このプロセスにおいて生成AIは生徒の「思考の伴走者」として機能するはずです。
例えば、生徒がテーマ選びに悩んだ時、生成AIは新しいアイデアを提案してくれます。集めた情報をどう整理し、どのように考えをまとめればよいかをブレインストーミングする際にも、生成AIは力を貸してくれます。発表やレポートを作る時も、生成AIが作った「たたき台」を参考に、自分の考えをより深く表現することが可能になります。
こうした新しい学び方を支えたのは、まさにGIGAスクール構想で整備された1人1台端末とクラウド環境でした。先生が一人ひとりの生徒に十分な時間を取れない場面でも、生徒が生成AIと協力して学べるようになったことは、かつての教室では想像できなかった学びのスタイルになるはずです。
さらに、こうした探究的な学びが注目されると、大学入試制度にも波及する可能性があります。総合型選抜(旧AO入試)などが広がり、一般入試だけでは測りきれない「思考力・表現力・主体性」を評価する大学が増えています。
こうした流れを受け、いわゆる進学校でも詰め込み型から探究活動に本格的に取り組み、探究の成果を大学入試の出願書類として提出するケースが増えています。生徒たちが探究のテーマ選びや自己推薦書・プレゼン資料作成で生成AIをどう活用するかが、大きな課題になっているのです。探究学習が進学や将来の職業選びに直結しているからこそ、「自分がどんなテーマを選び、何を学びたいのか」を言語化し、表現できる力がますます重要になってきます。
つまり、大切なことは、生成AIは決して理系だけの話ではないということです。たしかに、生成AIを「作る」という視点で見ると、情報系や数学系の分野が中心になりますが、実はそれだけではありません。生成AIは社会のあらゆる分野に広がり、「AIを使う人」「作る人」「支える人」という三層構造の中で、ほぼ全ての学問や仕事とつながる技術になっています。
例えば、「AIを使って教育を変えたい」という人なら教育学部や心理学部、「AIを作りたい」なら情報系・数学系の学部、「AIが社会で正しく使われるためのルール作りに関わりたい」なら法学部・公共政策系というように、自分の関わり方によって大学選びが大きく変わります。
生成AIと進路の三層構造(例)
| 観点 | 役割 | 主な進学分野 | 大学・学部例 |
| 使う人 | 生成AIを使って仕事や研究を行う | 文系・実学系(教育、ビジネス、看護、芸術など) | 教育学部、経済学部、デザイン学部 など |
| 作る人 | AIモデルを開発・改善する | 情報系・数学系 | 情報工学部、データサイエンス学部、理学部数学科 |
| 支える人 | インフラ、倫理、制度を整備する | 工学系・社会系 | 工学部(電気・通信)、法学部、公共政策学部 |
これは自動車産業を例にとっても同じです。車を運転する人・車という機能を活かす人、車を設計・開発する人、道路や法制度を整備する人がそれぞれ社会にとって必要不可欠な存在であるように、生成AIも社会の多様な人材によって支えられているのです。つまり、生成AI産業はこれからの社会インフラになる産業だと思います。
「自分がどの立場で生成AIと関わりたいか」を意識することが、大学選びや進路選択の大きなヒントになります。探究学習は、まさにその「問い」を立てる力を鍛える場です。生成AIは単なる便利なツールではなく、自分の未来を描くためのパートナーなのです。
だからこそ、これからの教育現場は生成AIを「思考の伴走者」として活用し、生徒たちが自分自身の未来を主体的に切り開いていくことを支援することが求められているのです。
高林の考え――教育に生成AIを導入する意味
私はこの生成AIの潮流に、迷わず突き進むべきだと思っています。
ただし、私たち大人が忘れてはいけないのは、自分たちの価値観や成功体験を子どもたちに押し付けないことです。かつて「24時間働けますか?」という言葉が称賛された時代もありましたが、今の子どもたちは違います。彼らは生成AIという新しい相棒もっというと友人と共に、新しい時代の学び方・働き方を選んでいます。「楽をしている」のではなく、「新しい時代に最適化した生き方をしている」のだと認識すべきです。
私たちが本当に考えるべきは、「生成AI時代における人間らしさとは何か?」という問いです。生成AIがあるからこそ、人間にしかできない「創造性」「倫理観」「共感力」を教育で育てることが、今後ますます重要になります。
まずは一度、大人たちは生成AIを使ってみてください。
大人が体験し、理解し、子どもたちの声に耳を傾ける。それこそが教育現場で生成AIを活用する真の意義だと私は思います。
ダブルノットの“ChatGPT初級編セミナー”のご案内
「AIと対話しながら、仕事の進め方を変える」その第一歩を、一緒に体験してみませんか?
ダブルノットの“ChatGPT初級編セミナー”は、生成AIをこれから会社に導入したい・使ってみたい経営者の方や、自分自身で少し使ってみたけれど活用しきれていないという方向けの入門プログラムです。
大切なのは“AIに任せる”ことではなく、“AIとともに考える”ことです。
セミナーでは、生成AIの基本的な知識と使い方をわかりやすく解説し、実際の業務でどのように活用できるのかを10時間で学んでいただけます。
まるで運転教習所に入る感覚で、この講座を通じて、生成AIという新しい相棒との付き合い方を身につけてみませんか?
毎週メルマガ配信中!
生成AIなどのデジタルに関する最新情報や、代表・高林の見解を毎週メルマガでお届けしています。ぜひこちらからご登録ください。