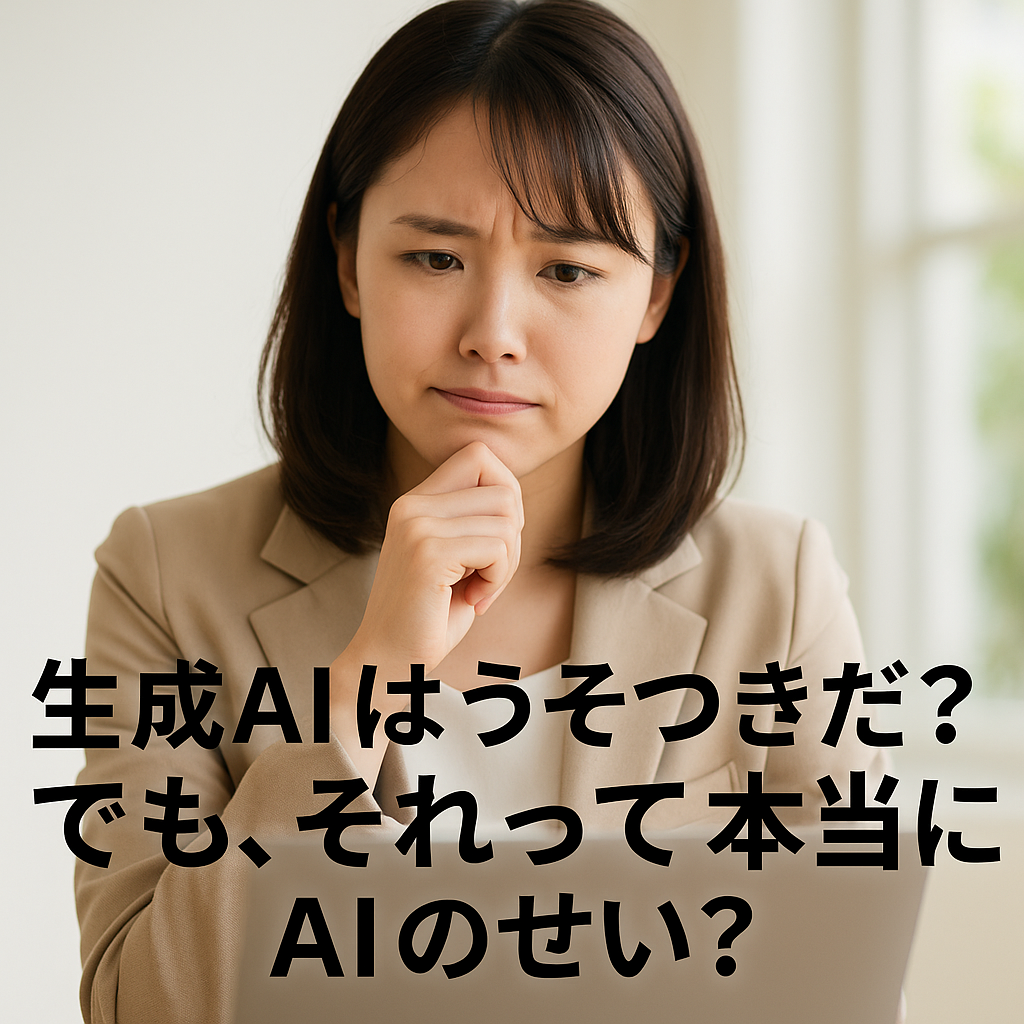2025年1月にネット店長育成塾第四期生として受講いただいた、「平山牛舗」の平山さんにインタビューさせていただきました!
兵庫県養父市で但馬牛を中心とした精肉販売を行う「平山牛舗」。100年近い歴史を持つ老舗として地域に根ざす一方で、より多くの人に但馬牛を届けるため、ネット販売の強化にも取り組まれています。
ご家族で店舗運営に携わるなか、平山和貴さんとその妻・美穂さんは、次の平山牛舗の成長戦略を考えるうえで、「デジタル戦略、とくにネット販売の強化は避けて通れない」と感じていました。大枠の方針づくりを担う和貴さんに対し、美穂さんはその実行面を担う役割としてネット店長育成塾を受講されました。
今回は、美穂さんに受講のきっかけや、講座で得た学び、受講後の変化についてお話を伺いました。
兵庫県養父市で但馬牛を中心とした精肉販売を行う「平山牛舗」の紹介はこちら
売上を伸ばす“次の一手”が見えずにいた私が、受講を決めた理由
以前からBASEを活用してECサイトを運営しており、約1年前にホームページと統合する形でサイトのリニューアルを行いました。ネット上の環境は整ったものの、売上アップにつなげる施策までは手が回らず、注文が入ったら対応するのに精一杯の状態が続いていました。
そんなタイミングで、弊社のスタッフがダブルノットのセミナーに参加する機会があり、ECサイトの支援の取り組みについて知りました。そのことがきっかけで興味を持ち、ネット店長育成塾の受講を前向きに検討するように。当時の私は日々手探りでECサイトを運営していたため、短期間で実践的な基礎が学べるという点に魅力を感じ受講を決めました。
「これで合ってる?」が自信に変わった。実データで“自社の課題”と向き合えた講義
少人数制の講座だったこともあり、課題への丁寧なフィードバックや質問対応など、一人ひとりにしっかり時間をかけていただける環境がありました。そのおかげで、「こんな初歩的なことを聞いても大丈夫かな?」と迷うような内容も気兼ねなく相談でき、大変ありがたかったです。また、週1回の個別面談では、講義中に解決しきれなかった疑問点もじっくりフォローしていただき、理解を深めることができました。
講義では自社の実データを用いて課題に取り組めたため、非常に実践的で、自社の課題をそのまま学びに活かせる内容でした。たとえば、顧客対応に関する講義ではメールのテンプレートや対応方針を見直すことができました。足りない点を具体的に指摘いただけたのはもちろん、課題への回答について「問題ない」と評価していただけた部分もあり自信につながりました。実務で活かせているだけでなく、社内でも内容を共有し、全体のレベルアップにつながっています。
さらに商品ページ作成の講義では、「買い手目線」に立ち返ることの大切さに改めて気づかされ、自社の強みを再認識する機会にもなりました。文字の縁の色といった細部まで具体的なフィードバックをいただけたことで、実際のページ改善にも直結しています。
「何から始めればいい?」から一歩前へ。事業計画とコンテンツづくりで動き出せた
受講前は、ネットショップの売上を伸ばしたい気持ちはあっても、「何から手をつけたらよいかわからない」という漠然とした不安を抱えていました。講座を通じて、ひとつひとつ課題が明確になり、今やるべきことが具体的に見えてきました。なかでも、自社のデータを元に事業計画を立てられたことは大きく、これから進むべき道筋が見えてきた実感があります。
現在は施策のひとつとして「コラムの更新」に取り組んでいます。以前はなかなか記事を増やすことができない状態でしたが、講義で学んだコンテンツ作成の考え方を活かし、月に1本を目安に新しい記事の執筆を始めています。また、日々の業務には生成AIも活用しており、業務効率化にもつながっています。
さらに、事業計画の講義では「数字」にしっかり向き合うことができました。売上をプラスにするためにどこを見直すべきか、どんな数値を目指すべきかが明確になり、正直なところ「このままではいけない」という危機感を持ったほどです。その結果、今まであまり関わってこなかった「商品価格の設定」についても意見を出すようになり、自分自身のネットショップ運営への関わり方にも変化が生まれました。
コンテンツ作成・商品ページの改善・価格戦略の見直しなど、やるべきことはまだまだあります。講座で得た学びと気づきを活かし、これからも試行錯誤を重ねながら、但馬牛の魅力を全国に届けていきたいと思っています。
ネットショップ運営者向け講座・ネット店長育成塾に関するご相談やお見積もりのご依頼は、下記よりお気軽にご連絡ください。